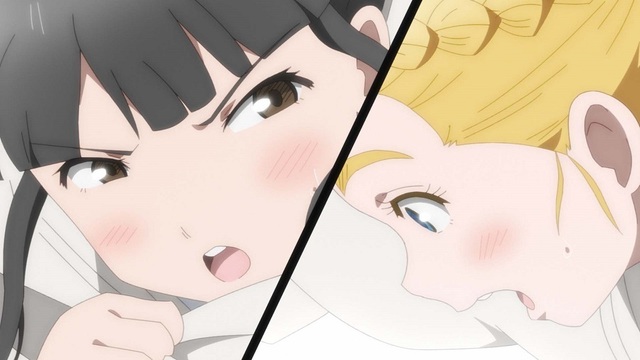2023年1月〜3月に放送され、青春女子柔道作品として人気を博したTVアニメ「もういっぽん!」。
原作は、村岡ユウ先生による同名漫画(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載。2023年4月からは無料まんがサイト「マンガクロス」にて連載中)。柔道経験者である村岡先生が描く柔道シーンは秀逸で、試合の熱さやワクワク巻、青春の尊さを描いたストーリーも魅力だ。
今回のアニメでは、監督に荻原健さん、シリーズ構成に皐月彩さん、キャラクターデザインに武川愛里さんを迎え、原作のよさを生かしつつアニメとしての魅力もプラスされたことで、視聴者からの評判は回を重ねるにつれて上がっていった。
そんな本作はどのように作られたのか。アキバ総研では、本作のアニメーションプロデューサーであるBAKKEN RECORDの大松裕さんにお話をうかがった。前編に引き続きお楽しみいただきたい。
キャスティングは意見が分かれることなく実力重視で決定
――チームワークという話が出ましたが、作品やキャラクターを作るうえではキャストも重要な要素です。メインとなる青葉西高校柔道部のキャスティングは、どのように決めたのか教えて下さい。
大松 キャスティングに関しては、特に条件や制限はなく、本当に実力重視で選びました。しかも、村岡先生にもキャスティングに参加していただき、先生を含めてすんなり決まったんですよ。僕は声優事情に明るくないので、誰がどう人気のある人なのかわからなかったのですが、意見が分かれることなく実力重視で選ばれた5人です。
――実際に演技を聞いての印象や、思い出深いことはありますか?
大松 今となっては反省点になるのですが、メインの5人が集まったのは第1話の収録だったんです。できればその前に、アイドリングのようなことをやれたらよかったなと思いました。もちろん、皆さんすごく技術があるので最初から素晴らしかったんですけど、話数が進むにつれて作中のキャラクターと同じように、キャストの皆さんの関係性もこなれていって、お芝居にどんどんエンジンがかかっていくのをすごく感じたんですね。
特に金鷲旗(金鷲旗高校柔道大会)に入ってからのお芝居は本当によかったなと。最後のほうは強いお芝居が必要になってくるんです。このタイミングでこのお芝居をしないと作品としての力が弱くなる、といったところを5人が5人とも外さずやってくれたのは、すごく感心しました。
――収録を見ていて、それほど大変そうにしていた感じもなく?
大松 そうですね。僕は今回、それぞれの声優さん本人の延長線上にキャラクターがいるようなイメージを受けたんです。だから、「すごく作ってお芝居しました」みたいな感じではなく、ナチュラルに芝居をしているという印象を受けました。もちろん苦労は細かい調整はあったでしょうけど、皆さんの努力も相まってよいテンポで収録ができたと思います。
――金鷲旗ではそれぞれの心情や悔しさ、感情の機微がすごく出ていたように感じました。
大松 金鷲旗で試合をしない南雲は第6話が山場だったと思いますけど、未知も早苗も永遠も姫野も、金鷲旗に入っていろんな感情が出るので、そこを外さずにやってくれたのは素晴らしかったです。
――では、物語全体のこともお聞きします。全話を通して、大松さんが特に印象的に残っている話数やシーンをあげるならどこでしょうか?
大松 第4話ですね。最初に柔道をちゃんとやるのはこの話数なので、第4話はこのシリーズにとってベンチマークになると思っていました。それに、僕のミスでもあるのですが、実は演出が、最初にお願いしていた演出家から、途中で荻原監督に変更となったんですよ。
――たしかに、第4話は荻原監督自身が演出もされていますね。
大松 僕のミスを荻原監督がカバーしてくれて、コンテを直して自分で処理もやってくれました。ありがたいことに、満田(一)さんというスーパーアニメーターもそのタイミングで入ってくれて、回り込むカットとか柔道の描写に関してもすごく手応えを得られるフィルムになりました。
プロデューサーの上田(智輝)さんにも「自分で言うのもなんですけど、4話よかったですよね」と話をしたのをすごく覚えています。ここで外せばリカバーできないと思っていたので、ここを外さなかったのがシリーズを運命付けたというか、成功に導く道筋のひとつだったと思いますね。
――第4話は試合の描写もそうですが、永遠と天音の気持ちが織りなす青春感というか、演出がすごくよかったです。
大松 よかったですよね。大人になると、仲直りしたいなんて思わないじゃないですか。ダメだったらそいつとは一生ダメだ、っていう人生を送って久しいので(笑)。「仲直りしたい!」って感情が素直に尊いと思いましたし、それが動機になって柔道の試合をするところは村岡先生の天才的なところですよね。
永遠にしても天音にしても、ほんとにいろいろあったけど、この試合を通じて仲直りしたいという気持ちが美しすぎて。あまりスタッフには言えないですが、ひとりで号泣しちゃうぐらいよかったです。
――青春の尊さをこうきれいに描かれると、見ていて心が洗われます。
大松 今回、青春感の強い作品をやらせていただいて、僕自身はそんなに明るい青春時代を送ったわけではないですが、追体験するような気持ちになりました。青春はすごく短いものだし、エネルギッシュなものだし、尊いものなんだなと。
第2期は声をかけていただけたら真剣に考えたい
――最終話に関してはいかがですか?
大松 「もういっぽん!」の尺は、本編が20分20秒ぐらいですが、最終話はオープニングをつぶしてエンディングも特殊エンディングですから、合計で20分20秒+3分ぐらいあるんですね。内容以前に、土壇場でこんなことを物量的にやれるのか?というのがありました。23分強の映像を作ることは非常にハードルが高いので、まずはそこが大きな課題だったと思います。
――特殊エンディングの中身も面白かったですね。原作にある、大会後にみんなで海に行ったシーンが最終話のエンディングで描かれていて。
大松 オフショットのような感じですね。この作品は衣装がそんなに変わらないので、ちょっと違う衣装を着せてあげたいという思いもありました。
――エンディングといえば、そこまで珍しい手法ではないかもですが、話数が進むにつれて人が増えていったのもよかったです。オープニングも途中から5人バージョンのカットになりましたし。
大松 僕からすると、ただでさえ本編が大変なのに、こんな小ネタみたいなことはやめてくれと思っていたんです(笑)。でも、意外と言ったらあれですけど、皆さん喜んでくれて。これに味をしめたので、いろんなアニメでやっていこうと思いました。
――エンディングは当番回に合わせたソロパートも、制作スタッフわかっているなと。
大松 そのあたりの仕掛けは、ポニーキャニオンさんのアイデアでやりました。5人分のキャラクターを(追加で)描かなきゃいけないのは大変でしたけど、やった甲斐のあるエンディングになりました。
――オープニングやエンディングは当然アニメオリジナルのものですが、本作では原作からの大幅な変更や丸々アニメオリジナル回を入れるといったことがなく、原作を上手にアニメ化した印象がありました。
大松 本当に胸を貸していただいたというか、大事な原作をお借りした、という思いがありました。原作のイメージを壊さずに、終わったらお戻ししなきゃいけないと。そういう意味では、(アニメ化にあたり)細かな部分の修正はありましたが、お借りしたものを汚さずにお返しできたという安心感、達成感はありますね。
――そしてやっぱり、視聴者からは第2期を望む声が上がりました。個人的にも原作の続きをアニメ化して欲しいと思っているのですが、それに関してはいかがでしょうか?
大松 そこは正直、僕が決めることではない、としか言えないです。アニメスタジオって何年先までスケジュールが決まっていますからね。ただ、この作品はポニーキャニオンの上田さんが企画されて、彼の思いに共鳴してやらせていただきました。上田さんには最後の最後まで熱心に伴走していただき、とても感謝しています。なので、もし次の機会があるのであれば、真剣に考えたいと思います。僕も改めて続きを読み返したら、いいエピソードがたくさんあるんですよ。デザインにしても今回インフラを作りましたから、話が来たら改めていろいろと整理をして、新たな気持ちで取り組みたいなと思っています。
BAKKEN RECORDのコンセプトは「デジタル化」と「インハウス化」
――この機会を借りてBAKKEN RECORDについてもお聞きします。タツノコプロが立ち上げた新レーベルとのことですが、どのような経緯で誕生したのでしょうか?
大松 タツノコプロは偉大な名前ですし、これまでやってきたことや(創業者である)吉田竜夫先生の理想には、心の底からリスペクトしています。それに、僕はProduction I.G出身なので、石川さん(Production I.G設立者で現在は代表取締役会長の石川光久氏。タツノコプロ非常勤取締役)がタツノコプロ出身であることを考えれば、僕にもタツノコプロのDNAが流れていると思っていますから。
ただ、言葉を選ばずに言うと、制作スタジオとしては停滞しているなと思ったんです。それに、新たなビジョンでモノを作りたいときには、偉大なタツノコプロという名前が、逆にじゃまをしてしまうかもしれないなと。そんな僕の傲慢さを当時の社長が認めてくれて、「お前の言う通り、新しい名前でやっていこう」と生まれたのが、BAKKEN RECORDです。
――レーベルのコンセプトや、どのようなことを目指しているのかも教えてください。
大松 大事にしていることが2つあります。それは、「デジタル化」と「インハウス化(内製化)」。この2つがレーベルとしての大事なコンセプトです。
――アニメの制作現場の現状も踏まえて、それをコンセプトに掲げた理由をお聞かせください。
大松 ここ数年アニメ制作における考え方や方法論は、ものすごく変わってきたと思うんです。2023年の冬クール(1月〜3月放送アニメ)も6本ぐらい延期があったじゃないですか。延期になることが珍しくなくなったぐらい、アニメの制作はひと昔前に比べてとても難しくなっているんですね。それを考えると、「フリーランスを集めて解散」「また集めて解散」とやるのは、再現性がないというか。ある種、無理ゲーに近くなっているんです。よいモノを作る以前に、そもそもちゃんとしたアニメーションを作るためには、インハウス化は避けて通れないんですよ。
なので、遅きに失した感はありますが、今年の4月からうちも社内のアニメーターをごっそり社員化しました。本当によいモノを、再現性を高めて作っていくなら、京都アニメーションさんやufotableさんがやってきたことをやらざるを得ないと思ったんです。それで、インハウス化を大きなビジョンのひとつとして掲げました。
――それは「もういっぽん!」でも生かされたのでしょうか?
大松 そうですね。社内プロパーの子たちはまだ若いですけど、若いからどんどん伸びるんですよ。シリーズを通してこんなにうまくなるのかと思うことが多く、すごく手応えを感じました。このチームでやっていけば、どんどんレベルの高いものを作っていけるという実感がありましたので、これはインハウス化する一番大きなアドバンテージだと思いますね。
チームでやることで素晴らしい作品を生み出したい
――日本のアニメ自体が、ひと昔前とは世界の中で置かれている状況が変わってきていると思いますし、そういう意味でもインハウス化は必要だという認識なわけですよね。
大松 商業アニメの歴史を振り返ってみると、東映アニメーション株式会社(設立時の社名は日本動画株式会社)や、それに追随して虫プロ(虫プロダクション株式会社)が始まった頃って、アニメーターは会社員だったわけですよね。その後、リストラや倒産などがあり、1980年代あたりからフリーランスで皆さんが活躍されるという流れになるのですが、僕は先祖返りしている感覚があるんです。フリーランスが集まって作ることに僕自身はすごく慣れているし、素晴らしさもあるんですけど、昔はいろんなことをもっとディスカッションして制作していたんだろうなと以前から思っていました。インハウス化することによって、ようやくそれができます。
やっぱりアニメって、コミュニケーションを取ってイメージを共有化すればするほどよくなっていくものなんです。なので、1960年代頃のアニメスタジオがやっていたことを、令和の時代に改めてやっていくことは、先祖返りでありつつ新鮮な気持ちもあります。僕もキャリアは20年以上になりますが、改めてアニメ制作に対してすごくワクワクしてますね。
――作品の話をうかがった際、「チームワーク」という単語を使っていましたけれども、インハウス化でひとつのチームとして作っていく色が強くなる感じでしょうか?
大松 もちろんそうです。京都アニメーションさんがなんであんなに素晴らしい作品をずっと作れていたのか、よくわかります。チームでいろんな話をして、細かな情報共有を積み重ねていく。あそこまでのクオリティになったのは、やっぱりチーム感の賜物なんですよ。「チームを作って解散」「また作って解散」ではなく、ずっと同じチームでやること、蓄積された時間の長さが素晴らしい作品に繋がるのをしみじみと実感します。我々もチーム感を高めていって、いい作品をアウトプットしていきたいですね。
――その話に関連して、最近ネットで「アニメーターの人の話をもっと聞きたい」といったことが話題になっていまして。その中に、アニメーターはキャスト以上に作品やキャラクターと向き合っているという発言もありました。ひとつのチームとして向き合うことで、キャラクターがより生きてくることもありそうですね。
大松 あると思います。すでに発表されている「Turkey!」という作品(長野県千曲市を舞台にボウリング部の女子高生5人が活躍する、BAKKEN RECORD×ポニーキャニオンのオリジナルアニメ)は、演出陣も社員3名を抜擢して制作していまして、コンテを描いている最中から定例会を開いているんです。コンテを描いているときに気づくこととか、共有したほうがいいと思うことって絶対にありますから。それによって、作品に対してもキャラクターに対しても理解が高まるし、なにより一番大事なのはモチベーションですね。モチベーションも、みんなで話すことによって高まっていくのを感じます。そういった現場の熱を、轟々と燃やしすぎると燃え尽きちゃいそうですけど、早いタイミングから火をともして、熱さを継続しながら最終話の納品まで行きたいと思っています。
――そういった人たちが手がけると、作品やキャラクターへの愛が視聴者に伝わりますからね。
大松 アニメって残酷です。手を抜こうと思ったら、いくらでも手を抜けるんです。ただ、それが簡単に視聴者に伝わるという恐ろしさがあるんですね。最初に言ったように、アニメは必要以上にしんどい作り方をしちゃダメだと思ってはいますけど、手を抜いてはいけない部分が必ずある。それをがんばれるかがんばれないかは、作り手のマインドによるところが大きいんです。そのマインドを高めていって、勝負どころの表現を(手を抜いて)流したものにならないようにする。そういったディテールの集積がよい作品になっていきますから、そういうチームにしていきたいと思っています。
――お話をうかがって、改めて「もういっぽん!」は作品やキャラクターへの愛や熱量を感じる作品だったなと思いました。
大松 そう言っていただけるのはありがたいですし、皆でがんばって制作した甲斐があります。
(取材・文/千葉研一)