アニメ制作会社の群像劇をアニメにする―これまでまったくなかった題材ではないが、オリジナルTVシリーズとして展開する「SHIROBAKO」は前代未聞の企画だった。昨年10月の放送を前にした評判の中には冷淡な意見もあったが、いざ放送が始まると職業ドラマとしての評判が広がっていき、最終的に大喝采をえて今年3月に放送を終えた作品だ。「SHIROBAKO」はそうしたオンエア中の評判だけでなく、ビデオパッケージリリースについても同時期放送作品のなかで屈指の売れ行きを示している。当初は内容説明すら難儀だった作品が「売れる作品」になったのにはどんな理由があったのだろうか。そのマーケティングとクリエイティビティについて、本作のビデオメーカーであるワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメントの川瀬浩平プロデューサーに話をうかがった。
普遍的な作品を作ったからこそ、潜在的なユーザーに受け入れられた
――アニメ制作会社を舞台にするという内容のアニメオリジナル作品が視聴者に好評を博し、ビデオグラムの販売も好調の様子です。現状をビデオメーカーのプロデューサーとしてはどのようにご覧になっていますか?
川瀬 実はこの作品って、オンエア前は製作委員会の中でも「ちょっと地味じゃない?」って印象を持たれていたんです。そこは僕としては予想をしていた部分ではありました。ただ、内容的に「アニメ制作会社」を舞台にしているので、お客さんの知的好奇心に訴える題材で、そこにスラップスティックなエピソードがあることで面白く見てもらえるだろうという自信は持っていました。
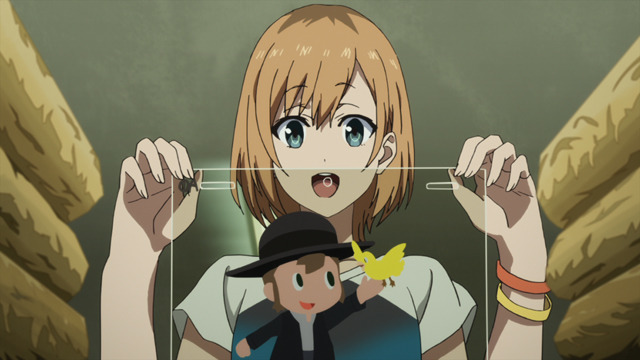
何より、もう10年くらいの付き合いがある水島努監督がタクトを振る以上はお客さんの見たいフィルムを提示してくれるだろうなと。なので、ヒットしたというのは1つの結果であると捉えています。無欲ではないんですけど、先ほどの前提があったのであまり楽観視していたわけでもありませんでした。我々としては「見てもらえたら喜んでもらえるだろう」という思いで、制作中は突き進んでいたような気がしますね。
――プロデューサーのお仕事というのは多岐にわたっているかと思いますが、代表的な内容を教えていただけますか?
川瀬 僕のやり方でいうと、最初にコンセプトを伝えます。ただ、本作に関しては制作会社のP.A.WORKSの堀川社長と水島監督がそれぞれ明確な主張をお持ちでしたので、それらをどう面白く見てもらえるか、どうやったらその意志が通じるかを考え、お客さんとの間をつなぐ役を担当しました。つまり、こういう題材の時にはお客さんはこういうものを欲しがっていると理解し、それをクリエイティブ側に伝えていきます。いっぽうで、プロデューサーというのはプロモーターとしての側面もあって、クリエイターが作ったものをより多くの人に見てもらうために広げていく土台作りの仕事もあります。具体的には弊社宣伝担当や制作サイドと連携しながら、さまざまな方法で「この作品を見て損はないよ」という入り口を作っていきます。ただ、我々は種をまくだけで、作品を育てるのはあくまでお客さんだと思います。今のお客さんは個人でいろいろな発信ツールがあるからおのおので広めてくれるし、そうして「面白いらしいぞ」と評判になったら、みんなそこに入ってきてくれます。今回はそうした良い循環を特に如実に感じられた作品だったと思います。
――ビデオパッケージについても、最初から人気が爆発したというよりも、口コミが作用したかのように徐々に増えていって、一時期は入荷したそばから売り切れてしまうという、最近のアニメでは珍しい売れ行きを示していたように見えましたが、その様子をメーカープロデューサーとしてはどのようにご覧になっていましたか?
川瀬 確かに今回の商品の売れ方は特殊だったかと思います。最初に手応えを感じたのは今年の1月の2クール目が始まった頃くらいでした。ちょうど12月末にBD/DVDの第1巻を発売したらすぐに売り切れてしまったんです。ビデオパッケージの受注を締め切るのがだいたい発売の1か月前、オンエアでいうと第7~8話ぐらいの頃ですから、アニメオリジナル作品ということもありお客さんもまだ様子見をされていたと思うんです。そのときの数字で第1巻を卸して、あとから盛り上がっていったからスロースターターな売れ行きになったのかなと。あと、この作品が2クールだったということもあると思います。毎期4~50本の新作がオンエアされる中、見る作品を絞っていた方がこの作品の評判を知って、ちょうど1クールが終わる頃に一挙上映会を行なったのでそこで見て追いついて2クール目からいっしょにご覧になったことで、お客さん全体の盛り上がりが大きくなって、それが販売に結びついた形になったんだと思います。
――購入されたユーザー属性についての分析はありますか?
川瀬 僕らの中で話したのは、ふだん買わないユーザーが買ってくれたのかもしれないということでした。それは、ああいう内容だったからなのかもしれないです。”本質”で買ってくれるお客さんに恵まれたのかなと。

――”本質”というのは?
川瀬 要は今のユーザーのトレンドに合わせて作った作品ではないということです。ある種、10年後に見ても楽しめるという普遍的な内容のものを作ったからこそ、ああいった売れ方をしたのかなと思います。つまり、「第1巻がリリースされたけど、もう古くなってしまったからいいや」ではなく、「やっぱりこの作品は買って置いておかなきゃ」と思ってくださる潜在層に訴えられた作品性だった。だからこそ、続巻も安定して購入し続けてくれているのかなと思います。
――商品としてみても、映像資料やブックレットなどアーカイブ性のある特典内容が魅力的に映りました。
川瀬 その点については当初から目指したところでした。お客さんがこの作品を気に入るとしたらフィルムの中身だろうし、それを楽しく見るためにもっと知りたいことってなんだろうと考えました。やっぱり作品性と合った商品特典でないと意味がないですから。たとえばこの作品の方向性から言って、特典にキャラクターソングを付けるのは違うと思うんです。アニメ制作の裏側を題材にしている作品だからこそ、お客さんは「裏側を作った人たちの裏側」を知りたいだろうということで、宮森あおい役の木村珠莉さんに制作現場レポートをしてもらったり、40Pを超えるブックレットを制作経験のあるライターさんに書いたりしてもらいました。それらの特典アイテムでフィードバックしてもう一度フィルムを見てもらうことでより面白さに気づいてもらうことが商品としては重要なんじゃないかなと。
――それに関していうと、公式サイトの用語集とか、制作の流れを説明するページなど、視聴者の疑問や興味にしっかりと応える作りだったのも本作の特徴だったかと思います。
川瀬 あれは制作陣とも話して、最低限の用語は公式サイトでフォローするしかないだろうP.A.WORKSさんにもご協力いただいて制作しました。用語について制作陣は当然わかっているけど、視聴者の方にとってはどれが特殊かっていうのが逆にわからないのでみんなで寄ってたかって、ひとつずつ文章を作っていったんです。
――今や視聴者の皆さんはすっかり鍛えられたと思いますが、オンエア前は何が通じるのか分からないですよね。それこそ、Aパート・Bパートって言葉が何を指すのかとかも。
川瀬 そうですね。そもそもタイトルの「白箱」からして通じない(笑)。VHS時代の制作見本ですからね。今だったら箱じゃなくてディスクですから「白盤」になるかと思いきや、未だこの業界では「白箱」なんですよね、不思議と(笑)。